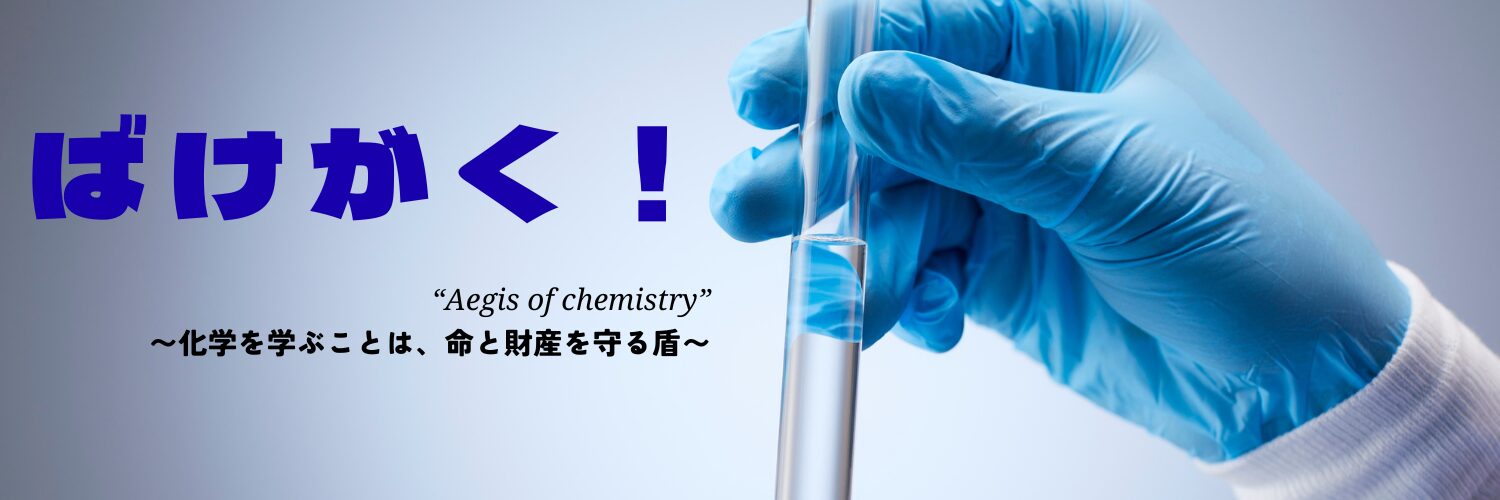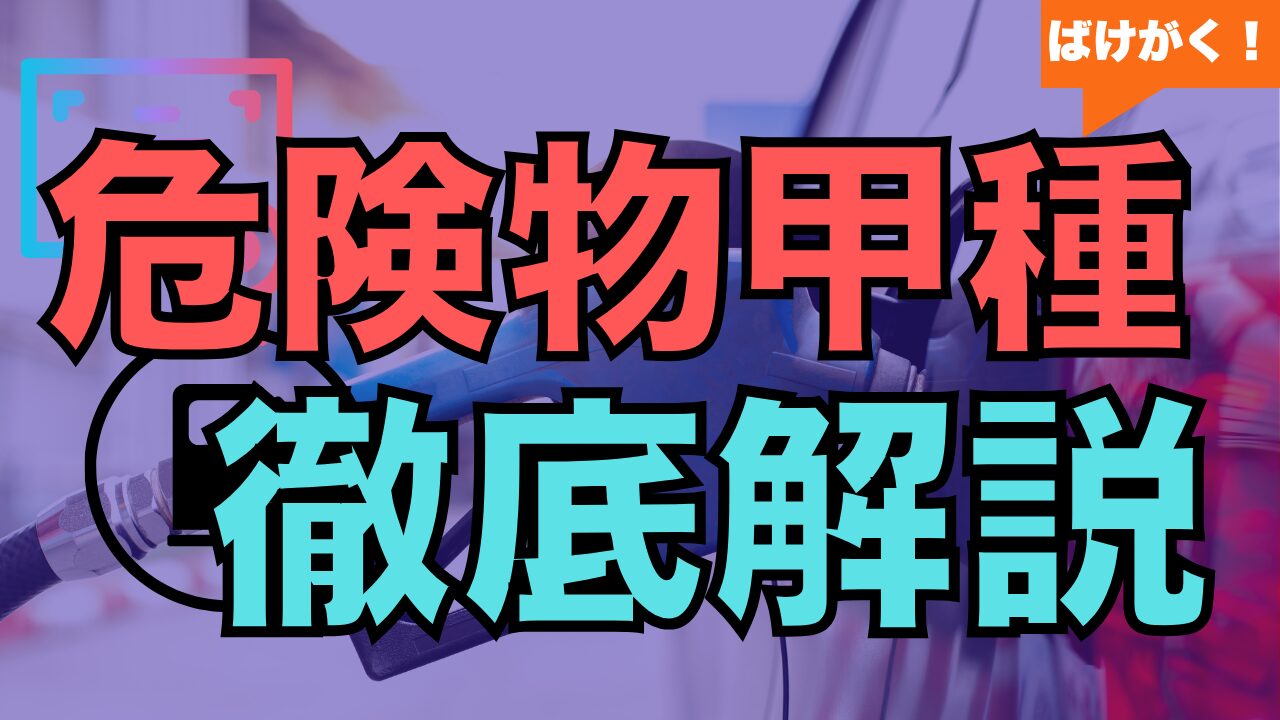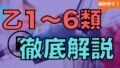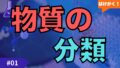結論
- 甲種は危険物の最上位資格。第1〜6類のすべてを扱え、指導・監督まで可能。
- 受験には学歴・乙種の組合せ・実務経験のいずれかが必要(※後述のチェックで判定)。
- 勉強は法令/物理化学/性質・火災予防の3本柱。模試→穴埋めが最短ルート。
- キャリアは安全管理・監督者・責任者で有利。手当・昇格・転職にも効く。
危険物取扱者は3種類(ざっくり比較)
| 種別 | できること | 受験資格 | 難易度の目安 | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|
| 甲種 | 第1〜6類すべて+指導・監督 | 要件あり(学歴 or 乙種の組合せ or 実務) | 高い | 管理・安全責任/監督者を目指す |
| 乙種 | 選んだ類のみ(1〜6類の中から) | なし | 中 | 現場で必要な類をピンポイントで取りたい |
| 丙種 | 第4類の一部(ガソリン等)取り扱いのみ | なし | やさしめ | 限られた作業を早く許可範囲内で行いたい |
まずは現場で必要な乙種から→複数乙で甲種へが王道。
すでに要件を満たす人は甲種に直行でもOK。
甲種危険物取扱者とは?(できること)
- 第1〜6類すべての危険物を取り扱い・立会い・管理できる
- 現場作業者への指導・監督ができる(責任範囲が広い)
- 役割:安全管理・リスク評価・教育・手順整備 など
→ 管理職・リーダー・安全責任者を目指す人に強力。
受験資格チェック(3ルート)
次のいずれかを満たせば受験可。自分に当てはめてチェック👇
A. 学歴ルート
- 大学 or 高専で化学系を卒業、または化学に関する科目15単位以上 修得 → YESならOK
B. 乙種ルート(4枚セット)
- 次の4つをすべて保有:
- 第1類 or 第6類
- 第2類 or 第4類
- 第3類
- 第5類
→ 揃っていればOK
C. 実務経験ルート
- 危険物の取り扱い業務に2年以上 従事
→ 在職証明等があればOK
試験の中身と難易度
科目(共通3分野)
- 法令:定義/指定数量/貯蔵・移送・表示/許可・届出/罰則 など
- 物理・化学:燃焼・消火、熱・圧力、物性、基礎計算 など
- 性質・火災予防:第1〜6類の物質ごとの特徴と消火方法
難易度の感覚
- 範囲が広い+横断理解が必要
- 乙と比べて抽象度・理論の深さが上がる
- 合格率は概ね低め(会場・時期で変動)
→ “広く浅く”ではなく“頻出を深く正確に” が勝ちパターン
勉強時間の目安と配分
- 化学基礎あり:1〜2時間/日 × 約3か月が目安
- 時間配分の例:法令 35%|物理化学 30%|性質・火災予防 35%
- 法令は数字・用語のミスをゼロに
- 性質は「根拠→暗記」で記憶の定着
- 物理化学は計算より現象理解を優先(式は後追い)
最短合格ロードマップ(独学テンプレ)
Step 0|全体地図(1時間)
科目と出題範囲を地図化。何が分かれば合格なのかを可視化。
Step 1|頻出だけ先取り(6〜8時間)
法令の指定数量・表示/第4類の物性・消火/第1・6類の酸化・反応 など。
→ “ここだけで6割”の核を先に作る。
Step 2|模試→穴埋め(15〜25時間)
間違い=理解の穴。「なぜ×なのか」を1行メモで理由と根拠を紐づけ。
ノート作りすぎないのがコツ。
Step 3|横断比較(8〜12時間)
第1〜6類を表で比較(例:発火要因/禁水性/有効消火剤)。
→ 暗記が構造化されてブレない。
Step 4|直前仕上げ(4〜6時間)
- 法令の数字/標識/用語を一気見
- 苦手な類だけ図で復習(例:禁水→泡×、粉末○ など)
甲種のメリット(仕事がこう変わる)
- 全類扱える“万能”+指導・監督権限
- 安全管理・教育・監査の中心人材に
- 昇格・役職・手当の対象になりやすい
- 希少性(特に中小・地方拠点)で転職カードに
- 現場の“判断力”が上がる(事故未然防止)
活躍フィールド(具体例)
- 化学工場/石油化学プラント:危険物全般の統括・是正
- 研究施設:薬品管理・教育・プロトコル整備
- 物流・倉庫:危険物含む貨物の保管区分・標識・手順
- 消防・防災関連:リスクアセスメント/訓練/設備選定 など
よくある失敗と回避策
- 法令の数字で落とす → 一覧化して毎日1分確認
- 類の暗記が混ざる → 横断表で“似て非なる”を並べる
- 計算に時間をかけすぎ → 甲種は概念理解>計算。式は最小限でOK
- ノート沼 → 過去問の余白に1行メモ。作り込まない
FAQ(よくある質問)
Q. 甲種は独学でも合格できますか?
A. 可能です。頻出の先取り+過去問反復+横断表の3点セットが王道です。
Q. 乙をいくつか持っています。甲種に挑戦すべき?
A. 受験要件を満たすならGO。監督・教育まで視野に入るなら早めに。
Q. どの教材が良い?
A. まずは模試。補助として表で比較できる教材や動画を組み合わせると効率的。
Q. 合格率は?
A. 低めです(およそ30~40%)。だからこそ頻出の深掘りとケアレスミス対策が重要。
※ 受験条件・実施要領は地域で異なることがあります。最新の公式案内をご確認ください。
まとめ:最上位は“広く深く”。頻出から固めて一気に勝ち切る
- 甲種は最上位+指導監督でキャリアの武器。
- 要件チェック→頻出先取り→過去問→横断表が最短。
- 仕事直結の知識なので、学ぶほど現場で効く。
この記事が「化学っておもしろいかも」と感じるきっかけになったら、
高校化学を超わかりやすくフルアニメーションで解説している、
私のYouTubeチャンネル「ばけがく!」もぜひチェックしてみてください。
基礎から復習したい人も、受験や仕事に活かしたい人も、スキマ時間でサクッと学べます。