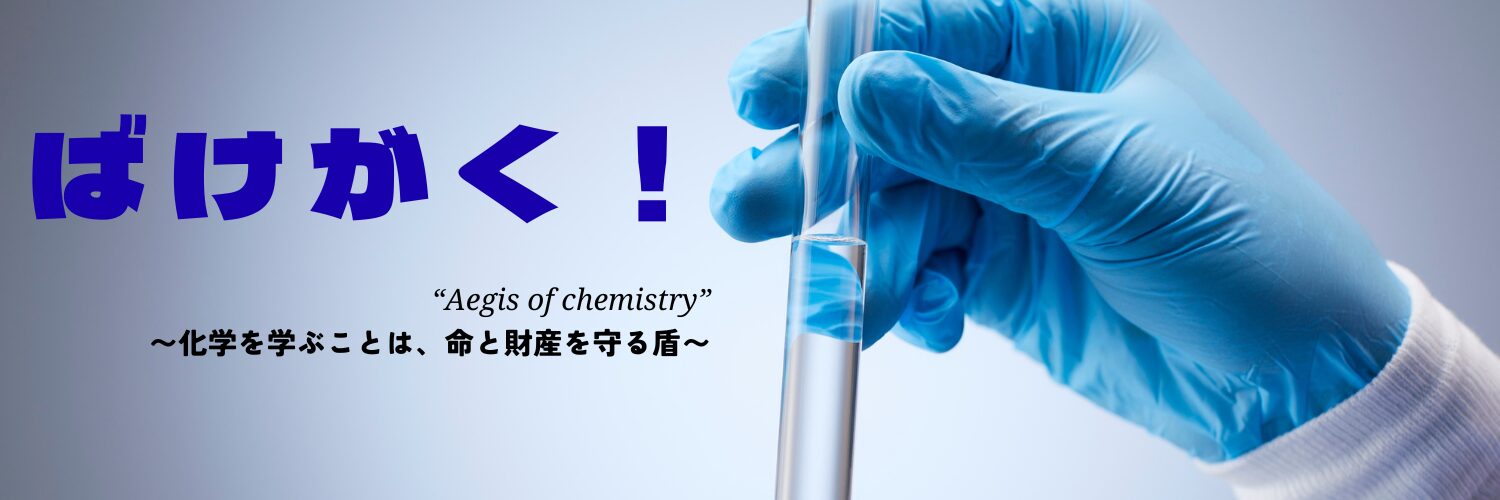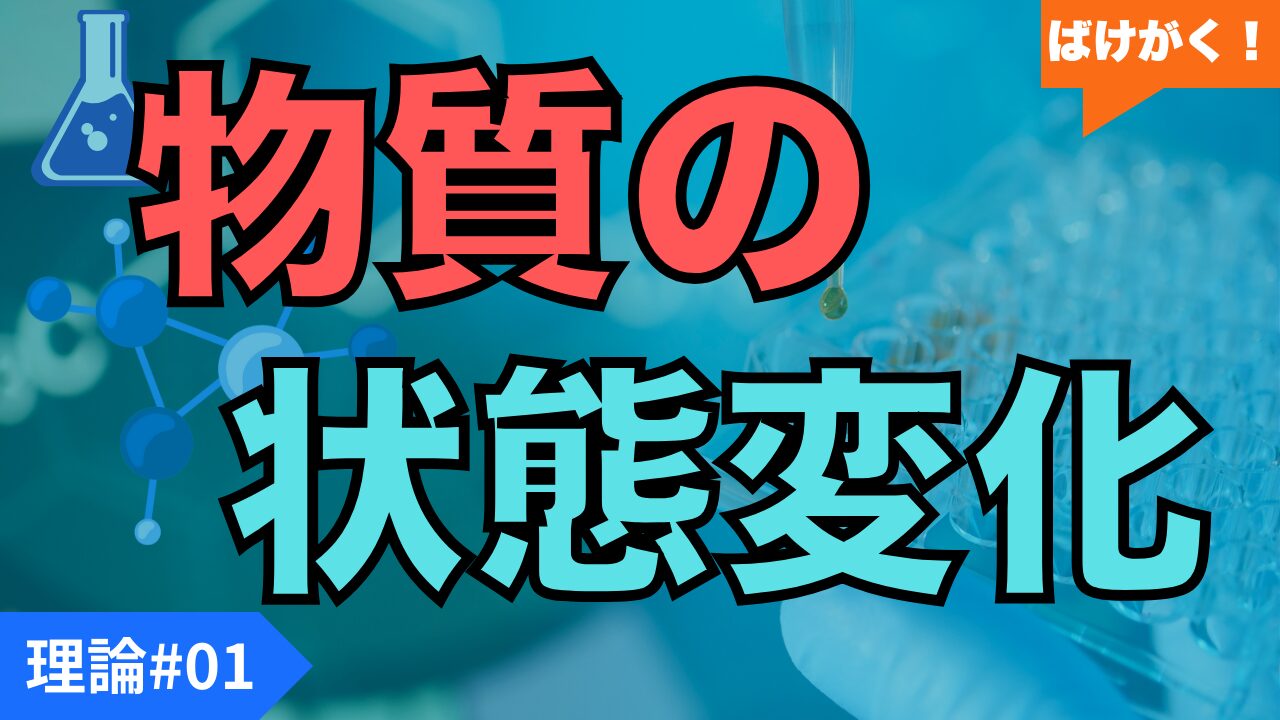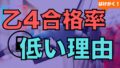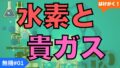🎥 動画で先にざっくり掴む:
今日のゴール
- 物質は固体・液体・気体の「三態」を行き来する
- そのたびに熱(エネルギー)の出入りがある(融解熱・蒸発熱など)
- 「分子間力」が強いほど、沸点が高く・蒸発しにくい
- 温度は分子の動きの激しさ。**K(ケルビン)**は
T = t + 273で換算
三態と名前(まず用語をサクッと)
- 固体→液体:融解(氷が溶ける)
- 液体→固体:凝固(水が凍る)
- 液体→気体:蒸発(水が沸く)
- 気体→液体:凝縮(湯気が水滴に)
- 固体→気体:昇華(ドライアイスが消える)
- 気体→固体:凝華(窓に霜ができる)
生活の例と結びつけると、暗記が一気に楽になります。
状態変化とエネルギー(“温度が止まる”理由)
状態が変わるとき、熱のやり取りが必ず起きます。
- 氷が溶けるときに吸収する:融解熱(水は約 6 kJ/mol)
- 水が沸騰して蒸気になるときに吸収:蒸発熱(水は約 41 kJ/mol)
- 逆方向は放出(凝固熱・凝縮熱)
ポイント:
- 温度計が0℃や100℃で“止まる”のは、入れた熱が分子どうしの引力(分子間力)を断ち切るために使われるから。
- 蒸発は引力を完全に振り切る必要があるので、融解より多くの熱が必要になります。
3) 分子間力が“蒸発しやすさ”を決める
液体の中では、分子どうしが弱く引っ張り合い(=分子間力)をしています。
この引っ張りが強いほど、
- 蒸発しにくい(=蒸発熱が大きい)
- 沸点が高い
代表的な2つだけ覚える
- 分散力:いちばん弱いが、分子が大きいほど強くなる
- メタン(小さい)→気体/ガソリンやロウ(大きい)→液体・固体になりやすい
- 水素結合:強い。水・アンモニア・フッ化水素など
- 水(H₂O)は常温で液体:水素結合が強いから
- 硫化水素(H₂S)は気体:電子の引き合いが弱く、水素結合が効きにくい
“水が特別に蒸発しにくい=分子間力が強いから”と覚えると、他分子との比較がスムーズ。
4) 温度と気体のふるまい(直感でOK)
- 気体分子はめっちゃ動き回る(=熱運動)→自然に拡散する
- 速い分子も遅い分子もいて、その割合は温度が上がるほど“速い側”が増える(マクスウェル分布のイメージ)
絶対温度(K)の換算
- 絶対零度:分子の動きが理論上ゼロ(−273℃)
- 換算式:
T(K) = t(℃) + 273- 0℃=273 K、100℃=373 K
まとめ(今日の3ポイント)
- 名前:融解・凝固・蒸発・凝縮・昇華・凝華
- 熱:状態変化では潜熱の出入り/蒸発は特に大きな熱が必
- 分子間力:強いほど沸点↑・蒸発しにくい/水は水素結合で特別
チャンネル登録のお願い
この記事が役立ったら、ぜひ YouTubeチャンネル「ばけがく!」 をチェックしてください。