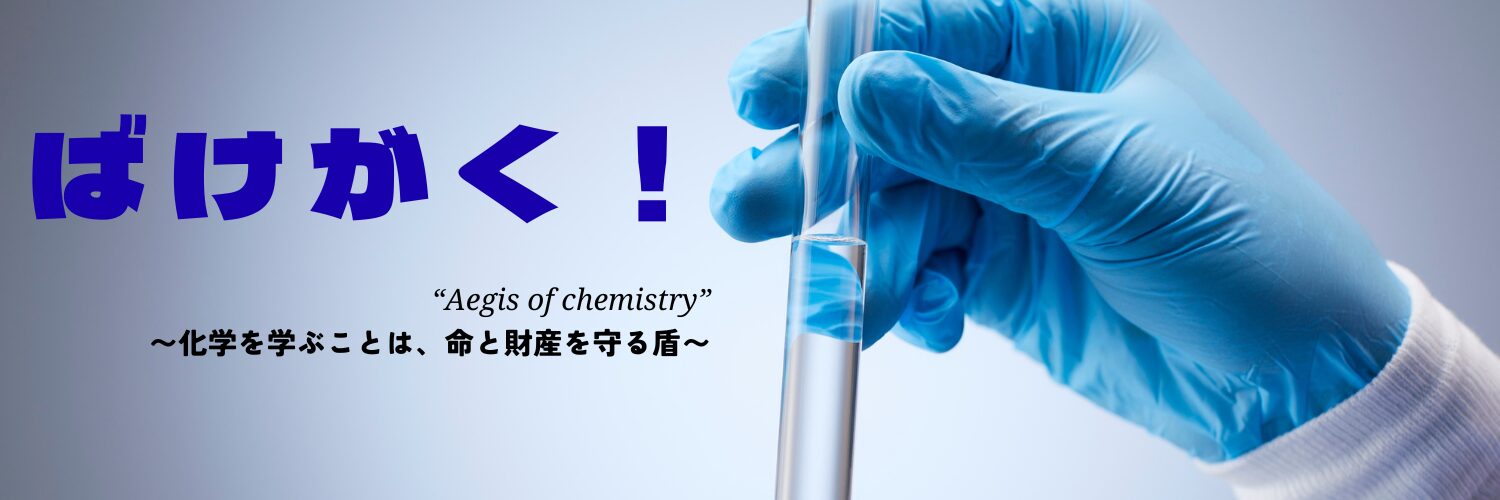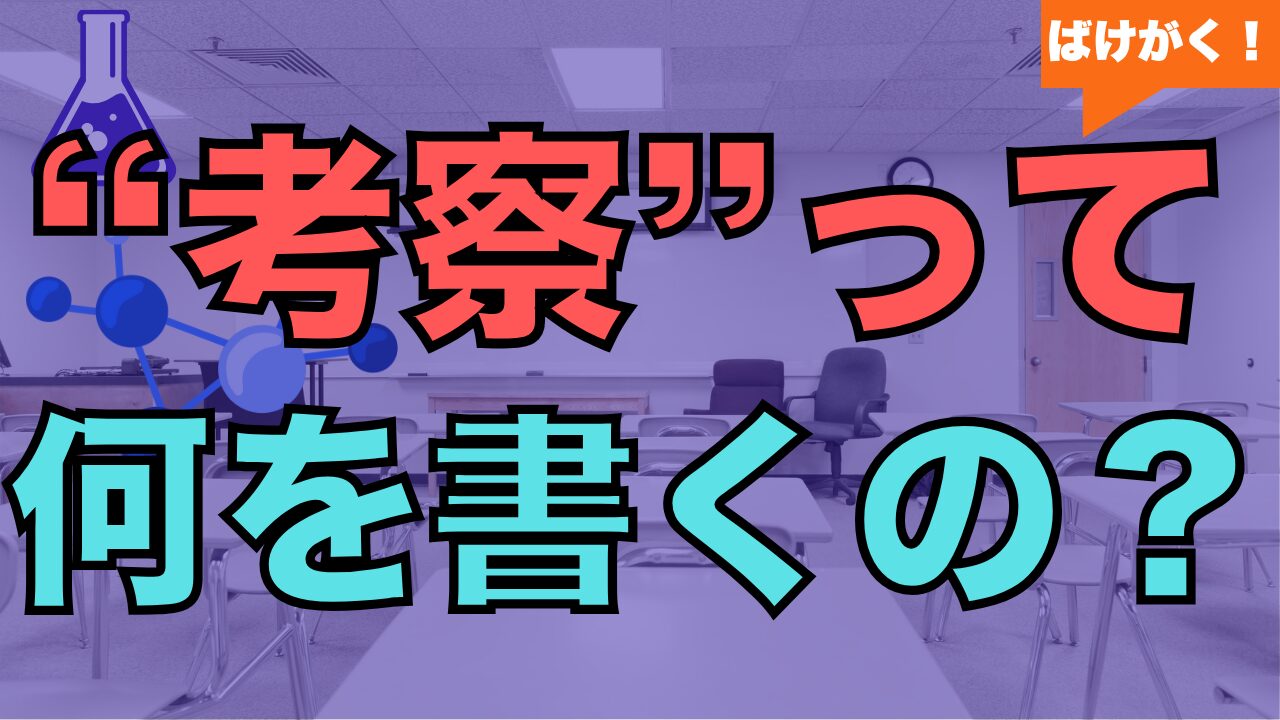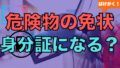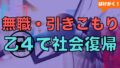理科や化学のレポートを書くとき、
「考察って何を書けばいいの?」「結果とどう違うの?」
と悩む人は多いですよね。
でも実は、レポートの中で考察こそが一番大事な部分です。
ここをしっかり書けると、レポートの完成度がぐっと上がります。
ポイント
・考察は「結果がなぜそうなったか」を、自分の言葉で説明するパートです。
・書き方は、結果を一文→理由(調べる)
→反省・工夫の3ステップで進めると迷いません。
・「結果・考察・感想」をきちんと分けるだけで、レポートが自然で読みやすくなります。
- 役割がハッキリ違う:結果=事実、考察=理由・意味、感想=感じたこと。混ぜないのが基本です。
- 考察は“なぜ”を説明する場所:感想ではなく、原理やデータをもとに理由を説明できると完成度が上がります。
- 型を真似できる:記事内で「結果→考察→感想」の例文が複数(10例)あるので、そのまま自分の実験に当てはめやすいです。
「結果」「考察」「感想」はぜんぶ違うもの!
まずは、この3つの違いをはっきりさせましょう。
| 項目 | どんな内容? | かんたんに言うと… |
|---|---|---|
| 結果 | 実験でわかった「事実」や「データ(数字)」 | 何が起きたかを書く |
| 考察 | 結果が「なぜそうなったのか」を考える | 結果の理由や意味を説明する |
| 感想 | 実験をやって思ったことや学んだこと | どう感じたかを書く |
たとえば炊飯に例えると、こんな感じです 👇
結果:米を炊いたが、全体がべちゃべちゃのごはんになった。
考察(理由):吸水量に対して水の量が多かったため、米のデンプンが過剰に水を含んで糊状になったと考える。
感想:見た目は悪かったが、やわらかくて意外とおいしかった。次は水の量を少し減らして再挑戦したい。
このように、
結果=「起きた事実」
考察=「その理由・仕組み」
感想=「気づき・次への意欲」
の順で考えてみましょう。
考察は「なぜ?」を説明する場所!
考察でやることはたった1つ。
それは、“なぜそうなったのか”を自分の言葉で説明することです。
考察を書くときは、次の3ステップを意識すると書きやすくなります。
① 結果を一文でまとめる
米を炊いたが、全体がべちゃべちゃのごはんになった。
② なぜそうなったのか考える(調べる)
吸水量に対して水の量が多かったため、米のデンプンが過剰に水を含んで糊状になったと考える。
③ 感じたことや反省、今後の工夫を書く
感想:見た目は悪かったが、やわらかくて意外とおいしかった。次は水の量を少し減らして再挑戦したい。
このように、
「結果 → 理由 → 感想」
の順で書けば、自然で読みやすいレポートになります。
よくある間違いに注意!
| よくある書き方 | どう間違ってる? |
|---|---|
| 「実験が楽しかった」 | ただの感想! |
| 「データがバラバラだった」 | 何が原因かを書いてない! |
| 「上手くいったのでよかった」 | 理由の説明がない! |
考察では、「どう思ったか」ではなく、「なぜそうなったか」を書くようにしましょう。
感想は“人としての気づき”を書くところ
感想の部分では、思ったことや学んだことを素直に書いてOKです。
「加熱の温度調整が難しかった。」
「チームで協力する大切さを感じた。」
など、実験を通して感じたことを簡潔にまとめると良い印象になります。
結果→考察→感想を10の例文で解説
① 酸とアルカリの中和反応
酸とアルカリの中和反応(塩酸水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を滴下)
- 結果:塩酸水溶液にフェノールフタレインを加え、水酸化ナトリウム水溶液を滴下すると、約12.0mLでうすいピンク色に変化した。
- 考察:塩酸中の水素イオンとNaOH中の水酸化物イオンが反応して水を生成し、pHが中性付近になったためフェノールフタレインが変色したと考えられる。
- 感想:色が一瞬で変わる瞬間がわかりやすく、1滴の違いで結果が変わるのが印象的だった。
② 電気分解(塩化銅水溶液)
- 結果:陰極に赤い固体が付着し、陽極からは気泡が発生した。
- 考察:電流によりCu²⁺が還元されて銅が析出し、陽極では水や塩化物イオンが酸化されたためと考えられる。
- 感想:金属が実際に見える形で出てきたのが面白かった。
③ 蒸留実験(エタノールと水の分離)
- 結果:最初に蒸発した液体の温度は約78℃で、においが強かった。
- 考察:エタノールの沸点が水より低いため、先に蒸発して分離できたと考えられる。
- 感想:温度計の読み方や冷却のタイミングが難しかった。
④ 炭酸水素ナトリウムの熱分解
- 結果:加熱すると白い粉末が減り、気体と液体が発生した。
気体は石灰水を白く濁らせた。
液体は塩化コバルト紙を青色から赤色に変化させた - 考察:炭酸水素ナトリウムが加熱で分解し、炭酸ナトリウム・CO₂・H₂Oを生じたため。
- 感想:目に見える変化があり、分解反応のイメージがつかみやすかった。
⑤ 植物の光合成実験
- 結果:光を当てた葉ではデンプンが検出され、暗い場所に置いた葉では検出されなかった。
- 考察:光がないと光合成が行われず、デンプン(有機物)が作られなかったため。
- 感想:理科の教科書で見た内容を、自分の目で確かめられて面白かった。
⑥ 鉄と硫黄の反応
- 結果:加熱後、磁石で引き寄せられなくなり、黒色の物質ができた。
- 考察:鉄と硫黄が化学的に結合して、硫化鉄になったため、性質が変化した。
- 感想:見た目も性質も変わる「化学変化」を実感できた。
⑦ 比例定数の測定(オームの法則)
- 結果:電圧と電流のグラフが直線になり、比例関係が確認できた。
- 考察:電流は電圧に比例し、抵抗が一定であることを示している。
- 感想:理論と実験が一致していて、電気の性質がよくわかった。
⑧ 液体の密度測定
- 結果:水の密度は約1.00 g/cm³、エタノールは約0.79 g/cm³だった。
- 考察:分子の大きさや結合の違いにより、エタノールの方が分子間のすき間が大きく、密度が小さい。
- 感想:数値の差にしっかり理由があることがわかっておもしろかった。
⑨ 化学反応の質量変化
- 結果:閉じた容器内では、反応前後の全体の質量は変わらなかった。
- 考察:化学反応では原子の数が変わらないため、質量保存の法則が成り立っている。
- 感想:質量が減らないのが少し不思議だったが、理屈を知ると納得できた。
⑩ 酸化と還元(銅と酸素)
- 結果:銅を加熱すると黒色に変化した。
- 考察:銅が空気中の酸素と化合して酸化銅(CuO)ができたため。
- 感想:金属が黒く変化するのを見て、酸化反応のイメージがつかめた。
💡 使い方のコツ
- 結果は「事実だけ」:数字・変化・観察を客観的に書く。
- 考察は「なぜ?」:理論や原理を使って説明する。
- 感想は「どう感じた?」:気づきや学びを短くまとめる。
まとめ:「考察=実験の理由を考えること」
- 結果 → 実験でわかったこと(事実)
- 考察 → なぜそうなったか(理由)
- 感想 → やってみてどう思ったか(気持ち)
考察は、ただの感想ではありません。
データや原理をもとに、自分の頭で“なぜ”を説明すること。
ここができると、先生にも「理解してるな」と伝わります。
ワンポイントアドバイス
- 「〜と考えられる」「〜が原因だと思われる」などの表現を使うと自然。
- グラフや数字を使って説明すると説得力アップ。
- 感想は最後に短く書くとまとまりやすい。
実験レポートは「やって終わり」ではなく、考えてまとめるところまでが実験。
「なぜ」を説明できるようになると、化学の理解がぐんと深まります。
この記事が「化学っておもしろいかも」と感じるきっかけになったら、
高校化学を超わかりやすくフルアニメーションで解説している、
私のYouTubeチャンネル「ばけがく!」もぜひチェックしてみてください。
基礎から復習したい人も、受験や仕事に活かしたい人も、スキマ時間でサクッと学べます。