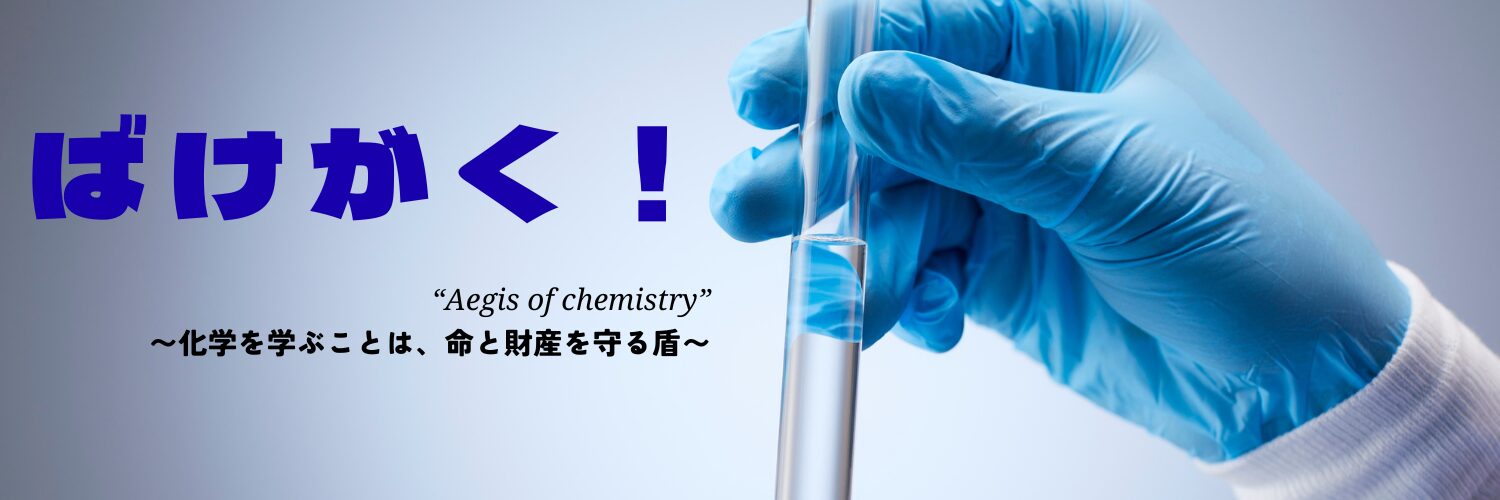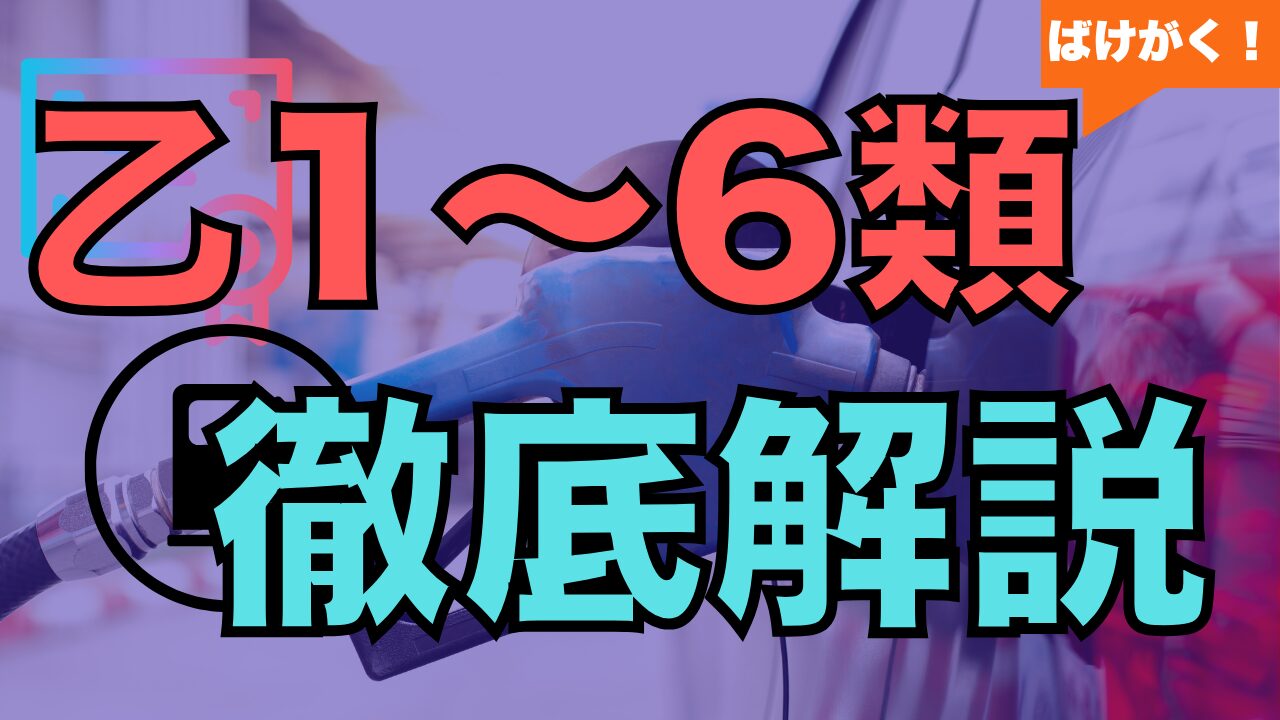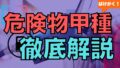この記事で分かること(要点)
- 乙種危険物取扱者の仕組み(1~6類の違い)
- どの類から取るべきかの判断基準(業界別のおすすめ)
- 試験範囲・出題科目・学び方の全体像
- 取得後のキャリア・実務での活かし方とメリット
解説動画はこちら
結論:迷ったら第4類(乙4)が無難
- 乙種は1~6類の中から必要な類だけ取得できます。
- 現場ニーズが最も広いのは第4類(引火性液体)。ガソリン・灯油・アルコールなど“身近&多用途”。
- ただし業界が決まっているなら、その現場で使う類から取るのが最短です(下表を参照)。
乙種危険物取扱者とは?(30秒で理解)
- 危険物を**6つのグループ(1~6類)**に分け、必要なグループだけ扱える資格。
- 取得すると、その類に対応する危険物の取り扱い・管理ができます。
- 受験資格は不要。独学OK・短期合格も十分狙えます。
1~6類のちがい(超ざっくり一覧)
| 類 | ざっくり性質 | 代表例 | よくある現場 |
|---|---|---|---|
| 第1類(酸化性固体) | “火を助ける粉” | 硝酸カリウム、塩素酸カリウム | 化学薬品の製造・保管、研究所 |
| 第2類(可燃性固体) | “こすれて燃えやすい固体” | マグネシウム粉、赤リン | 花火・金属加工 |
| 第3類(自然発火・禁水) | “空気/水で発火” | 黄リン、カルシウムカーバイド | 化学工場、農業資材 |
| 第4類(引火性液体) | “とにかく燃えやすい液体” | ガソリン、灯油、エタノール | ガソリンスタンド、石油関連全般 |
| 第5類(自己反応性) | “熱や衝撃で爆発性” | 過酸化ベンゾイル、アジ化Na | 製薬・実験室 |
| 第6類(酸化性液体) | “強い酸化力の液体” | 過酸化水素、硝酸 | 工業洗浄、化学プラント |
例:第4類=“液体の火種”。ガソリンなどが代表なので、実務の幅が広い=最初の受験に向く。
どれから受ける?(業界別おすすめ)
- 石油・燃料・自動車関連 → 第4類(乙4)
- 化学製造・原料保管・研究所 → 第1類(+必要に応じて2類/6類)
- 金属粉・花火・火薬周辺 → 第2類
- 農業資材・特殊反応を扱う工場 → 第3類/第6類
- 製薬・試薬・特殊化学 → 第5類
将来甲種を視野に入れるなら、複数類の取得が有利。実務+ステップアップの両面で効きます。
受験条件と試験科目(共通)
- 受験条件:どなたでも受験可(実務経験・学歴不要)
- 試験科目(共通)
- 法令(危険物の定義・貯蔵/表示/移送など)
- 物理・化学(燃焼・消火、性質、基礎計算)
- 性質・消火(各類の物質の特徴・消火方法)
メリット(現場&キャリアの“効き”)
- 取っつきやすい
受験資格なし。独学で短期合格も狙える。 - 必要な類だけでOK
仕事直結の一枚から始められる(ムダがない)。 - 現場での信頼・役割が増える
安全・保安の理解が深まり、任される範囲が広がる。 - 資格手当の対象になりやすい
会社によっては毎月の手当がつくケースも。 - 転職カードになる
工場・物流・研究所など横断的に通用。履歴書で光る。
活用シーン(具体例でイメージ)
- 化学工場:危険物の保管/表示/記録の適正化、安全教育の説得力UP
- 物流:危険物を含む荷役での手順遵守や書類確認
- 研究所:薬品の取り扱い標準化、新人教育の指導役に最適
- 燃料・販売:第4類を中心とした現場オペレーションの要
学び方(噛み砕き版・最短ステップ)
Step 1|全体地図をつかむ(1時間)
- 「法令」「物理化学」「性質・消火」の三本柱をざっくり把握。
- まずは自分の受ける“類”の現物イメージ(ガソリン=第4類、など)を持つ。
Step 2|用語→現象→理由(2~3時間)
- 例:「引火点」→いつ火がつく?→なぜ温度が関係する?
- 図・イラスト・写真を見ながら**“言葉を現物に結びつける”**。
Step 3|頻出論点だけ先に解く(2~4時間)
- 乙4なら引火点・蒸気・消火剤、表示・貯蔵の数字周りなど。
- まず“出るところ”だけで6~7割を固める意識。
Step 4|過去問で穴埋め(3~6時間)
- 間違えた問題=“言葉だけで理解していた”サイン。
- ノートは作り込まない。問題の横に1行メモでOK。
Step 5|直前まとめ(1~2時間)
- 苦手分野の超短い要点カードを作り、試験前に回す。
- 覚えにくい語は具体例(製品名)とアイコンで視覚固定。
よくある質問(FAQ)
Q1. 乙4の難易度は?独学でいけますか?
A. 独学で十分狙えます。“頻出論点だけ先に固める”作戦がコツ。引火点・蒸気・消火剤・標識・表示などを最初に。
Q2. 最初の1枚は何類が無難?
A. 迷うなら第4類(乙4)。実務の裾野が広く、学びが他の類にも応用しやすいです。
Q3. 何回分の模試を解くべき?
A. まず2~3回分で“頻出”を掴み、同じテーマを反復。広げすぎより“繰り返し”重視。
Q4. 甲種につなげたい。どう進める?
A. 実務に合う類を複数取りつつ、横断知識を意識。乙で鍛えた法令・性質の骨格がそのまま土台になります。
まとめ:必要な“1類”から。迷ったら乙4で“現場力”を底上げ
- 乙種は必要な類だけを短期で形にできるのが最大の魅力。
- 仕事に直結する一枚目から始め、実務→複数類→甲種というも描けます。
次のステップへ
この記事が「化学っておもしろいかも」と感じるきっかけになったら、
高校化学を超わかりやすくフルアニメーションで解説している、
私のYouTubeチャンネル「ばけがく!」もぜひチェックしてみてください。
基礎から復習したい人も、受験や仕事に活かしたい人も、スキマ時間でサクッと学べます。
ばけがく!【化学基礎・化学】
「ばけがく!」では、高校1年生~3年生向けの化学基礎・化学の授業をアニメーションで、わかりやすく・おもしろく・本質的にお届けしています。⸻「化学ってむずかしい…」「丸暗記ばっかりで、何してるかわからない…」そんなあなたにこそ見てほしい!映像...