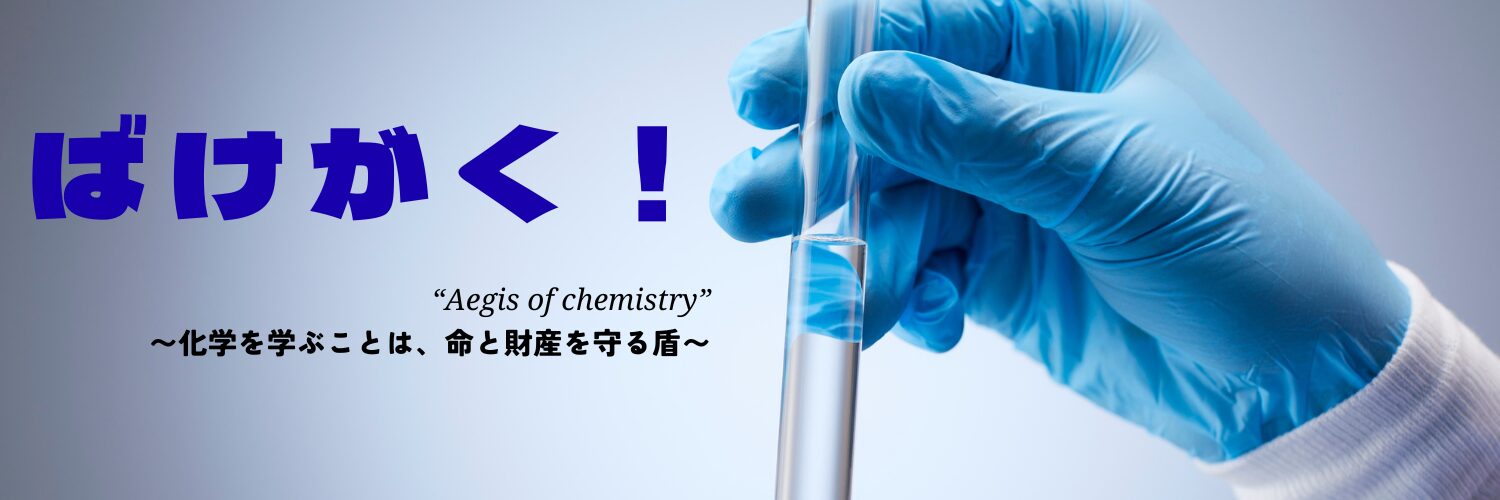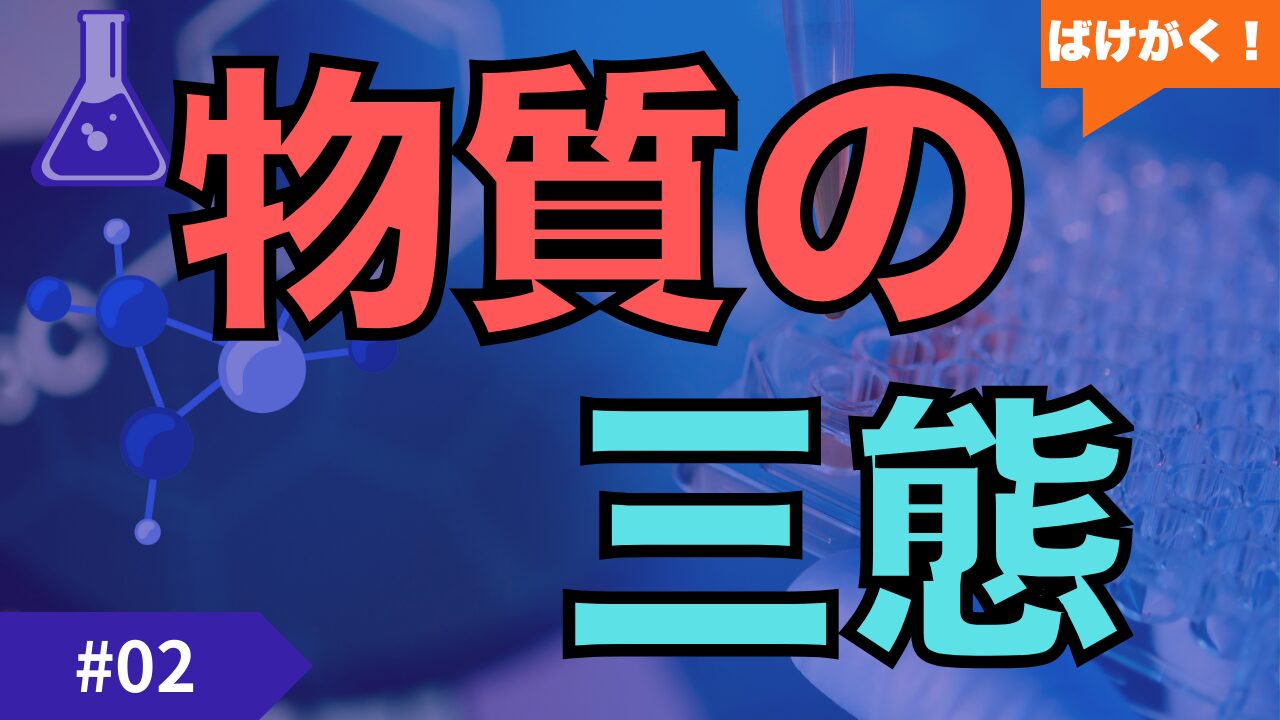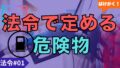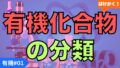この記事で分かること
- 三態(固体・液体・気体)と**相転移(状態変化)**の名前
- 熱運動・分子間力が“状態”を決める理由
- 沸騰と蒸発のちがい、気圧と沸点の関係
- 潜熱(融解熱・蒸発熱):なぜ温度が一時“止まる”のか
🎥 動画で一気に理解したい人はこちら:【高校化学基礎#02】物質の三態
この記事のゴール
- ものは固体・液体・気体を行き来する(=三態)。
- 名前(融解・凝固・蒸発・沸騰・凝縮・昇華・凝華)を身近な例で覚える。
- 「なぜ温度が止まる?」「なぜ山だと早く沸く?」を直感で説明できる。
1. 三態ってなに?(まずは例から)
- 固体:氷・ドライアイス・ロウソク
- 液体:水・食用油・アルコール
- 気体:水蒸気・酸素・二酸化炭素
同じ物質でも温度や圧力が変わると、姿(状態)だけが変わります。
例:氷 → 水 → 水蒸気(中身はずっとH₂O)
2. 名前セットを一気に覚える(家にある例だけ)
- 固体 → 液体:融解 … 氷がとける
- 液体 → 固体:凝固 … 水が凍る
- 液体 → 気体:蒸発 … 洗濯物が乾く(表面だけ静かに)
- 液体 → 気体:沸騰 … やかんがグラグラ(液体全体で)
- 気体 → 液体:凝縮 … お風呂の鏡に水滴
- 固体 → 気体:昇華 … ドライアイスが消える
- 気体 → 固体:凝華 … 冬の窓ガラスにできる“霜”
蒸発と沸騰のちがい:
- 蒸発=表面だけ・静か・常温でも起きる
- 沸騰=液体全体・激しく泡・沸点で起きる
3. なぜ状態が変わる?(分子の“綱引き”)
- 物質の中では、目に見えない粒(分子)がいつも動いている(=熱運動)。
- 一方で、分子どうしはくっつき合う力もある(=分子間力)。
- 分子間力(くっつく) vs 熱運動(離れたがる) の勝負で状態が決まる。
- くっつく力が勝つ → 固体
- いい勝負 → 液体
- 離れたい力が勝つ → 気体
たとえると…
友だちと手をつないで並ぶ(固体)→ゆるく手をつないで流れる(液体)→バラバラに走り回る(気体)
4. 温度が“止まる”のはなぜ?(潜熱のひみつ)
- 氷を温めると0℃でしばらく温度が止まる→それは、入れた熱が氷の結びつきを切るために使われるから。
- 同様に、沸騰でも100℃付近(常圧)で温度が止まる→液体から気体へ変わるためのエネルギーに使われる。
- この“状態を変えるためだけに必要な熱”が潜熱。
- 融解熱:固体→液体
- 蒸発熱:液体→気体(融解熱より大きいので、汗が蒸発すると強く冷える)
体感の例:手にアルコールをつけるとひんやり(蒸発熱で熱が奪われる)
5. 気圧と沸点(山と圧力鍋の話)
- 気圧が低い(高い山)→沸点が下がる
→ 高地でインスタントラーメンがぬるいお湯でも沸く感じ。 - 気圧が高い(圧力鍋)→沸点が上がる
→ 同じ火力でも中までやわらかく煮える。
6. よくある勘違い、ここで直す
- 「蒸発=暑い日にだけ起きる」 → ×。常温でもコップの水は少しずつ蒸発。
- 「泡が表面に見えたら全部蒸発」 → ×。沸騰は全体で気体が生まれている。
- 「氷と水は別の物質」 → ×。物理変化。中身は同じH₂O。
まとめ(3行)
- くっつく力と離れたがる動きの勝負で固体・液体・気体が決まる。
- 蒸発=表面/沸騰=全体。名前と身近な例をセットで覚える。
- 潜熱が使われている間は温度が止まる(融解・沸騰でよく見る現象)。
次の一歩(動画で理解を加速)
次回は 「#03 原子の構造」。
👉 チャンネル登録よろしくお願いします!