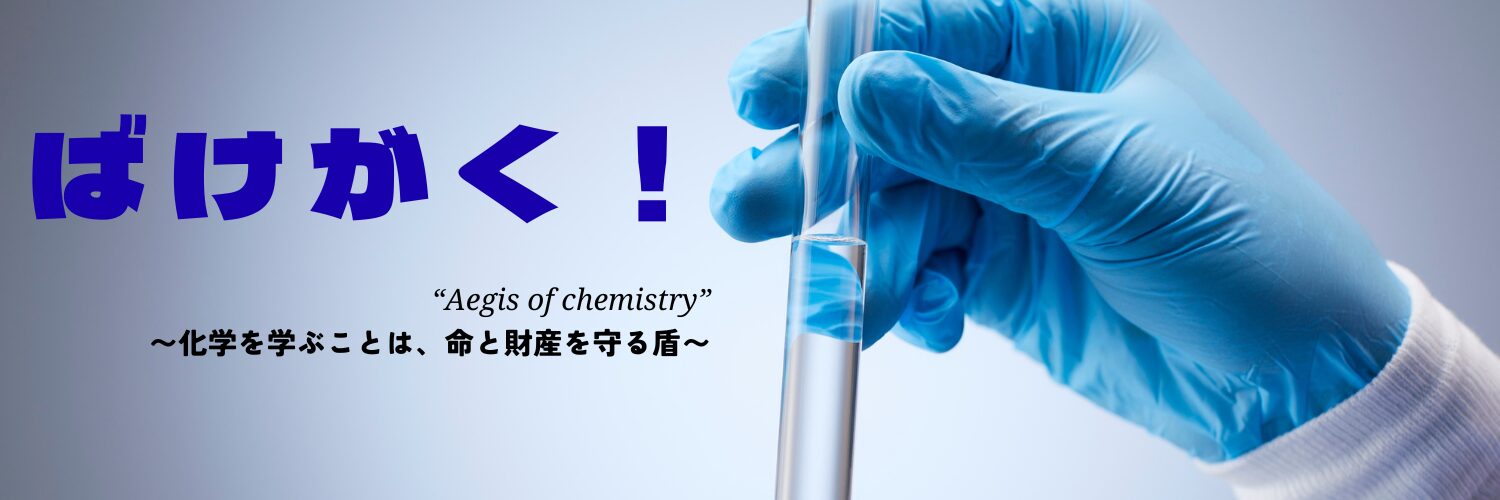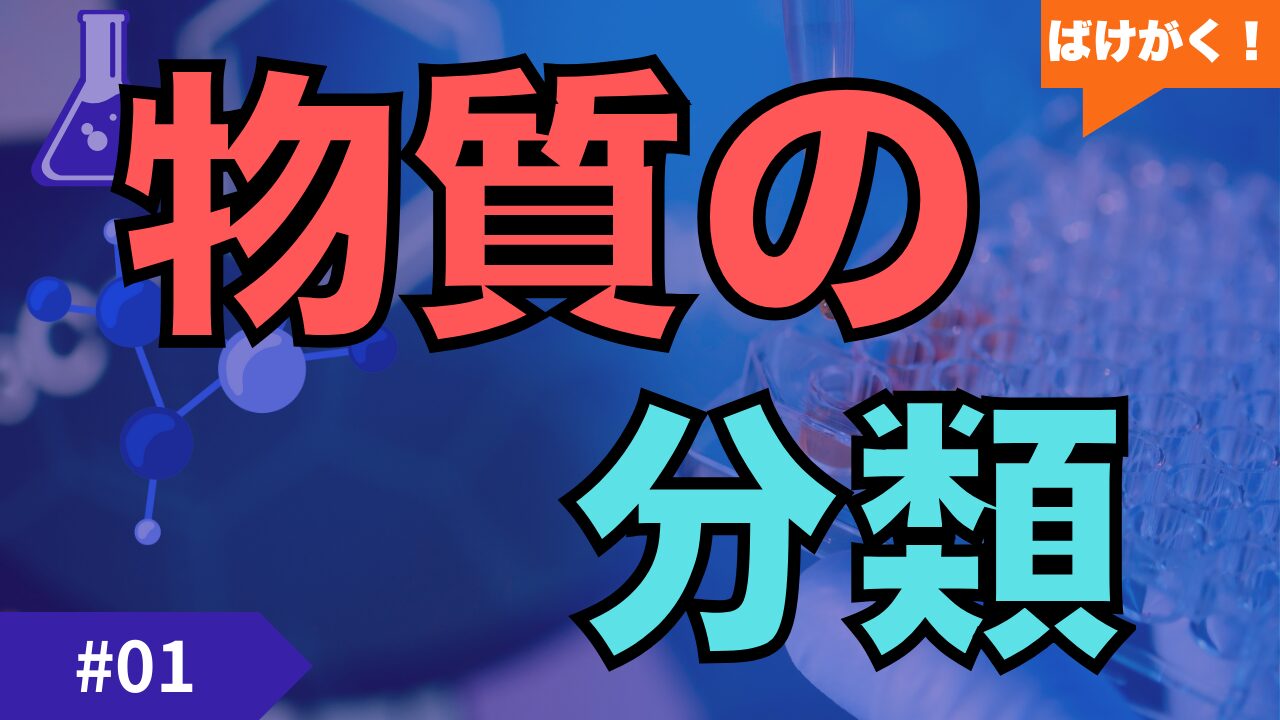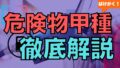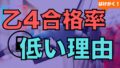この記事で分かること
- 「元素/原子/単体/化合物」のちがい
- 純物質と混合物の見分け方
- 同素体の代表例とゴロ
- 分離法(ろ過・蒸留・再結晶・抽出・昇華・クロマト)の使い分け
🎥 動画で一気に理解したい人はこちら:『ばけがく!』【#01 物質の分類】
まずは用語を最短で整理
- 原子:物質をつくる基本粒子(H, O, C など)
- 元素:同じ種類の原子のまとまり(“種類名”)
- 単体:1種類の元素だけでできた純物質(例:O₂, H₂, Fe)
- 化合物:2種類以上の元素が決まった比で結びついた純物質(例:H₂O, CO₂, NaCl)
単体も化合物も“純物質”。混ぜただけは混合物(反応していない)。
元素の確認・代表的な反応
炎色反応(元素ごとに炎の色が違う)
物質確認の定番
- 二酸化炭素:石灰水が白く濁る(CaCO₃の沈殿)
- 塩化物イオン(Cl⁻):食塩水+硝酸銀 → 白い沈殿(AgCl)
単体と同素体(同じ元素でも性質が変わる)
- 同素体:同じ元素からできているのに、構造や性質が異なる物質どうし
- ゴロ:「スコップ」= S(硫黄)C(炭素)O(酸素)P(リン)
代表例
- 硫黄 S:斜方硫黄(安定)/単斜硫黄/ゴム状硫黄(弾力)
- 炭素 C:ダイヤモンド(硬い・絶縁)/黒鉛(やわらか・導電)
- 酸素:O₂(無色無臭)/O₃(刺激臭・殺菌)
- リン P:黄リン(自然発火・水中保存)/赤リン(安定・マッチ)
純物質と混合物の見分け方
- 純物質:成分が1種類
- 単体:O₂, H₂, Fe …
- 化合物:H₂O, CO₂, NaCl …
- 混合物:成分が複数、反応せず混ざっている
- 例:空気、海水、砂糖水、ジュース
混合物は“分離”で元に戻せる(次章へ)。
混合物の分離法(何をどう分けたい?)
| 方法 | ねらい | 使いどころ・例 |
|---|---|---|
| ろ過 | 固体と液体を分ける | コーヒーの豆かす/泥水の砂 |
| 蒸留 | 沸点の差で分ける | アルコールの蒸留/海水→真水 |
| 再結晶 | 結晶として取り出す | 食塩の精製 |
| 抽出 | よく溶ける溶媒で成分だけ抜く | 紅茶のカフェイン抽出 |
| 昇華法 | 固体→気体→固体で分ける | ヨウ素、ナフタレン |
| クロマト | “走る速さ”の差で分ける | 黒インクの色素分離 |
クロマトって何?(色素のマラソン)
- よく溶ける色ほど遠くまで進む
- 紙にくっつきやすい色は手前で止まる
→ 黒インクが赤・青・黄に分かれる。
活用:食品分析/薬物検査/科学捜査
よく出る“ひっかけ”対策
- 氷と水:同じ化学式で状態が違うだけ → 同素体ではない
- 混合物?:分離で元に戻せるなら混合物(海水・空気など)
- 単体と化合物:元素の種類数で判断(1種=単体/2種以上=化合物)
まとめ(今日の3ポイント)
- 単体/化合物→どちらも純物質(“元素の種類数”で判断)
- 同素体は「スコップ(S C O P)」で代表例を覚える
- 分離法は“何をどう分けたいか”で選ぶ(表を思い出す)
次の一歩(動画で理解を加速)
次回は 「物質の三態」。
粒子は常に動いている?固体・液体・気体の世界をアニメで直感理解!
👉 チャンネル登録よろしくお願いします!